お客様プロフィール
| 紹介する機能 | 地力・生育マップ、生育ステージ予測、可変施肥&可変散布マップ |
| 地域 | 福島県 |
| 栽培作物 | 水稲(つきあかり、コシヒカリ、天のつぶ、ミルキークイーンなど)、タマネギ、ブロッコリー |
| 栽培面積 | 91ha |
| 従業員 | 6人 |
地域の農業を守るため、脱サラし農業法人を設立
ーー後藤さんは以前、サラリーマンだったそうですね。
相馬市にある実家が元々兼業農家でした。何代かにわたって、水稲を作っていたのです。会社員との二足のわらじですね。出稼ぎなども普通に行われていた時代ですから珍しいことではありません。家族で先祖代々の田んぼを守っていたという感じです。「私もいつかは」と思いながら一般の会社で働いていました。
そんな中で起こったのが2011年の東日本大震災です。田んぼや畑まで津波の被害がありましたからね。海の水につかり、流されてきたガレキも多く復旧は容易ではなかった。農業をあきらめるしかない人が現れるのも当然のことです。「このままでは地域の農業が廃れてしまう。引き受けるなら今しかない」と決意し、2013年末に会社を退職し、2014年1月から就農しました。
 代表取締役の後藤 直之さん
代表取締役の後藤 直之さん
ーー兼業農家ではなく、農業法人としたのはなぜですか。
親の農地は7haほど。正直、広くはないですね。両親は兼業を続けることを勧めてくれたのですが、自分の腹は決まっていました。最初に家の土地を引き継ぐことから始めても、離農する人が増えてくることは分かっていましたし、それを受け継ぎたい気持ちもありました。家族以外の人を雇う必要が出てくるでしょうから、法人にした方が良いという判断です。「息子は一度決めたら貫く人間」と親もわかっていたようで結局あきらめてくれました(笑)
2016年に法人を立ち上げ、従業員は現在6名が在籍しています。2019年にはライスセンターを建て、登録検査機関として農産物検査を行えるように米の農産物検査員の資格を取りました。自社の米を「福島県産」と銘打って売りやすくするといった企業努力も行っています。
 事務所横のライスセンター
事務所横のライスセンター
当初の7haが8年あまりで91haに限界を感じてリモートセンシングを導入
ーー急速に管理する面積が拡大したそうですね。
手広く農地を持っていた大先輩が規模を縮小することになり、その下請けが拡大の発端でした。「譲るからやれ!」という感じ(笑)。それで一気に20haくらい扱いが増えましたからね。他にも離農者が増えてきて、他の農家さんだってキャパが限られますから、私に引き継ぎの話が下りてくる。最近は落ち着いてきましたが、前年の5割増しの面積になることが続きました。今思えばですが、かなり無理をしていましたね。
ーーどのような問題があったのですか。
ご想像のとおり、圃場は近くに固まっているわけではありません。かなり広い地域に点在しています。面積が増えていく毎に管理の難しさを痛感することになりました。自分がすべての圃場を廻って状況を把握した上で水管理などの指示を従業員に出していましたから。実際40haになった年は手が回らず収量がダウンしました。それまでのやり方が限界を迎えたということです。従業員にエリアを預けて水管理や生育観察を任せてみましたが、一朝一夕にマスターできるわけではありませんし、なかなか苦労しましたね…。
ーードローンを導入してみたことがあると聞きました。
はい、5年ほど前にドローンを使ったリモートセンシングを試しにやってみました。最初の年は当時の農地60haのすべてを撮影してもらい、60万円近い費用がかかりました。しかし、撮影して解析するのに日数を要するため作業が手遅れとなることがあったり、その年のマップしか作ることができないなど、自分にとっては費用の割に満足できるものではありませんでした。
ザルビオを紹介されて導入
初年度から収量、売上が格段にアップ
ーー色々試した結果、ザルビオにたどり着いたのですね。
ドローンを購入までしていたのですが、利用していたサービスが中止になってしまったのです。高価な機械なのに今では倉庫番ですよ(笑)。それに代わるリモートセンシングとして勧められたのがザルビオでした。地力マップを活用して最初はお試しで、圃場2枚の可変施肥を行ったのが昨年のことです。
 ザルビオを操作する後藤さん
ザルビオを操作する後藤さん
ーー使ってみての最初の印象はいかがでしたか。
生育ステージ予測があるので、次の作業がいつになるか計画を立てやすいなと感じました。遠隔で状況を確認できるので、いちいち現場に向かう必要がない。私や従業員の労力を減らすことにもつながることがわかりました。ザルビオ上で生育が不安な場所はエリア担当に写真を撮ってもらったのですが、データと見比べてもズレは少なかった。ザルビオが信頼に値するものと実感しましたね。
ーー初年度の結果はどうだったのですか。
驚きましたよ!収穫の結果は反あたりの収量が約14%アップしたのです。これはザルビオ導入前には経験したことのない収量。的確な可変施肥と管理ができたおかげか、倒伏もなく、圃場全体が均一の出来。生育ムラがなく全体が良い稲に育ってので、この収量になったのでしょう。売上は昨年の価格でいえば約7000円/反のアップです。
半信半疑で試験的に使い始めたザルビオでしたが、今年は迷わず全ての圃場に導入することにしました。肥料を始めとする資材の価格アップに対抗できますし、新たな機材導入に向けた投資にもつながると期待しています。今のところ2024年も順調ですよ。
ーーザルビオの優れている点はどこだと考えていますか。
衛星が記録した地力マップの過去データが残っているのがありがたいです。お話ししたように離農された土地を引き継ぎ、新たな農地に取り組むことが毎年の通例。どんな性質の圃場なのかといった情報を持たないまま米を作り始めるわけです。しかし、ザルビオがあるおかげで初年度から安心して取り組めます。初年度であっても大事な1年ですから助かっています。
生育ステージ予測や植生マップもあるので、順調なら施肥を減らす、遅れているなら増やそうといった調整も判断がしやすい。現状、400枚の圃場で使用していますが、ザルビオのデータを基にして担当者に指示出しを行えるので、管理は非常に楽になりましたね。
 植生マップ
植生マップ
「まず、やりたいことを決める」がザルビオを上手く使うコツ
ーーザルビオは最初から上手く活用できましたか。
ザルビオって本当にできることが多すぎるんですよ。私も最初は訳がわからなくて困りました(笑)。でも役立つことは確実と思っていたので、とにかく触りまくりました。「習うより慣れろ!」です。自分の場合は元肥の可変施肥を成功させたかったので、地力マップを徹底的に。これが正解でしたね。地力に応じた量の肥料を記録した施肥マップを1週間前くらいに作って、USBでデータを連動可能な田植え機に読み込ませる。最初はこれだけです。「できることが色々あるから、あれもこれも全部見る」ではなく、「これを行いたいから、これだけを見る」が正解だと私は思っています。
ーー今後の経営やザルビオの利用について教えてください。
水稲は現在の91haを100haに。今の目標はここまでですね。それ以上は人材確保を始め、色々な投資を行わないといけないので。人がいないと草刈りや水の管理もままならない一方で、農閑期は作業が少なくなるため簡単に増員もできません。機械化、スマート農業化を進めながら従業員各々のスキルアップを行います。ザルビオも私以外が使えるようにするなど、より効率よく収益アップを目指します。
実は水稲の他に70㎞離れた場所でタマネギも作っているのですが、これを15haまで広げたいと思っています。ザルビオはタマネギにも使えるので、また触りまくって学ばないといけませんね(笑)。
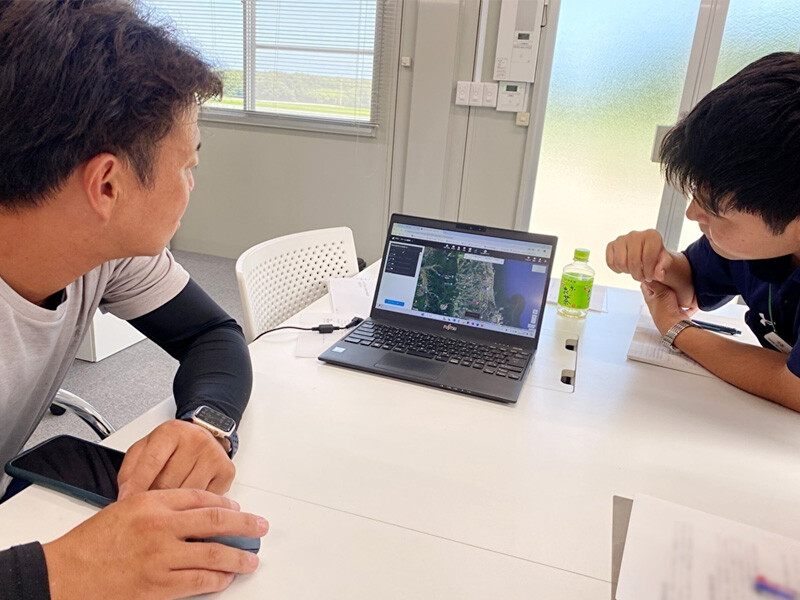 ザルビオの営業担当と今後の使い方について相談している様子
ザルビオの営業担当と今後の使い方について相談している様子

